気候変動への取組み
気候変動に対する考え方・方針
本投資法人は、気候変動を、あらゆる事業の存続に影響を及ぼしうる重要な外部環境の変化であると認識しています。気候変動は、地球規模において全ての生命や生活基盤、経済システムを広く脅かす重大なリスクであることから、国際社会としての対応が急務となっています。
我が国においては、2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを政府が宣言し、官民一体となった気候変動対応の取組みを加速させています。
本投資法人においても事業活動の円滑な継続のため、気候変動の抑制に資する「緩和」施策として、省エネ機器・高効率機器の積極的導入、テナントをはじめとするステークホルダーとの協働による省エネ・節水・3Rの推進、 再生可能エネルギーの導入など、2050年ネット・ゼロへ向けたロードマップ策定を進めます。また、気候変動による被害・損害の最小化に資する「レジリエンス向上」施策として、防災・減災を意識した資本的支出の最適化、ポートフォリオ及び個別物件におけるBCPの策定を推進します。
こういった活動をステークホルダーの皆様にお伝えし、対話を進めていくことを目的として、TCFD提言に賛同のうえ、TCFDフレームワークに沿った気候変動に関するリスクと機会への対応状況等について、今後も適時適切な開示を行ってまいります。
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同
本資産運用会社は2022年2月に、TCFDに賛同いたしました。
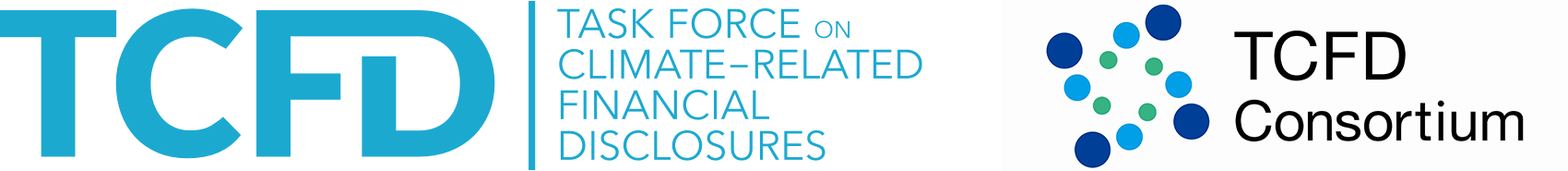
(TCFDが推奨する開示項目)
この表は左右にスクロールできます。
| 開示項目 | 開示内容 |
|---|---|
| ガバナンス | 気候関連リスク及び機会に関する当該組織のガバナンス |
| 戦略 | 組織の事業・戦略・財務計画に対して気候関連リスク及び機会が与える実際の影響及び潜在的な影響 |
| リスク管理 | 気候関連リスクを組織が識別・評価・管理するプロセス |
| 指標と目標 | 気候関連リスク及び機会を評価・管理するための指標と目標 |
ガバナンス
本資産運用会社ではサステナビリティ推進委員会を設置し、具体的な目標や施策の検討、進捗状況の把握を行っています。委員会は代表取締役社長、常勤取締役、投資運用部長、財務企画部長、コンプライアンス・オフィサーで構成され、決算期毎に一回以上開催されます。
サステナビリティ推進委員会の内容をはじめとするESG活動全般について半年に1回本資産運用会社の取締役会に報告され、経営課題としてのリスクと機会を共有しています。
戦略
本項目の記述に際しては、「2021/3国土交通省:不動産分野TCFD対応ガイダンス」における「参考シナリオ」を使用しました。4°C、2°C/1.5°Cそれぞれのシナリオにおける世界観は、下記のとおりです。ターゲットは概ね2030年~2040年としました。
- 「4°C」の世界観:気候変動対策よりも従前の経済活動が優先され、化石燃料への依存を続けた結果、気温上昇が放置され自然災害が激甚化・深刻化している。食糧事情の悪化・水資源等をめぐるトラブルが発生。種の絶滅や人類の活動に極めて大きな影響を及ぼしている。物理リスクの影響が比較的大きい。
- 「2°C/1.5°C」の世界観:社会全体で脱炭素化や社会全体で低炭素化や炭素回収、有効利用を推進することにより、気候変動緩和に一定程度の効果がもたらされ、気温上昇が抑制された結果、深刻な悪影響と危機的状態は回避できている。移行リスクの影響が比較的大きい。
この表は左右にスクロールできます。
| リスクと機会 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 移行リスク | 政策・法規制 | 4°C: 法規制対応は比較的少ない |
| 2°C/1.5°C: GHG排出に関する規制強化、情報開示義務拡大に伴う事務コスト増、環境税や炭素税の負担によるコスト増 |
||
| 技術 | 4°C: 既存設備のリプレイスは比較的少ない |
|
| 2°C/1.5°C: 既存設備のリプレイス頻度上昇、もしくは新技術の導入が義務化されることに伴うコスト増 |
||
| 市場 | 4°C: エネルギー・水・廃棄物処理などの価格高騰に起因する運用コスト増 |
|
| 2°C/1.5°C: 再生可能エネルギー調達に起因する運用コスト増 |
||
| 評判 | 4°C: ステークホルダーの低炭素社会への移行への意識に大きな変化は現れない |
|
| 2°C/1.5°C: ステークホルダーからのネガティブスクリーニングを受けることによる、投資主価値棄損。テナントの嗜好変化に伴い、環境対応が遅れている不動産が敬遠されることによる空室増と収入減 |
||
| 物理リスク | 急性 | 気象災害の激甚化・深刻化が顕著となり、これらに起因する不動産の物理的損傷や人的被害の発生、事業停止、復旧費の増加、従業員やテナントの安全・健康への大きな影響に伴うコスト増リスク |
| 慢性 | 気象パターンや人々の生活パターンや思考が変化し、これらに起因する設備損耗の高頻度化、損害保険料の上昇や浸水対策などのBCP・予備的コスト増となるリスク | |
| 機会 | 総合型の強み | 本投資法人は総合型のため様々なアセットタイプを組み入れることができるため、中・長期のリスクを勘案しながら、強靭なポートフォリオの構築を行っていくことが可能 |
| メインスポンサーがデベロッパーであることの強み | 本投資法人のメインスポンサーであるMIRARTHホールディングス株式会社においては、環境への取り組みの一環として、開発する不動産の一定数を環境不動産(第三者による認証や評価を受ける等、環境に配慮した不動産であることが示されているもの)とする旨のKPIを策定しており、本投資法人向けのパイプライン物件においても一定数が環境不動産となることが期待できる | |
| 再エネ調達有利の強み | 本投資法人のメインスポンサーであるMIRARTHホールディングス株式会社及びグループ会社において、クリーンエネルギー関連事業を行っている組織や会社が複数あり、将来的な協業や事業提携を検討中。グループ内の専門家によるコンサルティングを受ける等、メリットを享受しながら再エネ調達の有効手段について具体的施策の検討が期待できる |
※レジリエンス強化等の施策に伴う具体的なコスト試算・事業インパクト評価については外部専門家と協働し、今後順次開示していく予定です。
リスク管理
本資産運用会社では「リスク管理マニュアル」を定め、当該内容を実践しています(※下記一部抜粋)。また、気候変動を含めた、本投資法人の事業活動におけるリスク全般について、「リスクに係る管理方針の年間計画」を毎年改定し、社外委員が構成員に含まれるコンプライアンス委員会、ならびに取締役会において、当該計画について承認決議を行っています。リスク管理状況については自主点検や内部監査により問題が無いかを定期的に確認し、確認された内容は、必要に応じてコンプライアンス委員会および取締役会に報告されています。
本資産運用会社のリスク管理にかかる組織体制については、「G.ガバナンス リスク管理」をご参照ください。
(1) 取締役会取締役会は、当会社が抱えるリスクの種類と特性を認識したうえで、リスク管理に関する組織体制及び規程を整備する等リスク管理に関する重要事項を決定するものとする。
(2) コンプライアンス委員会コンプライアンス委員会は、組織横断的な協議機関としての役割を担い、リスク管理に関する組織体制及び規程等の制定・改廃の協議・検討及びリスクのモニタリング等を行い、リスク管理に関する重要な事項について決議を行うとともに、取締役会、監査役及びコンプライアンス・オフィサーと随時連携を図るものとする。
(3) リスク管理統括責任者コンプライアンス・オフィサーは、当会社のリスク管理を統括する役割を担うものとする。
(4) リスク管理責任者各部長は、所管する部門のリスクについての管理を行い、管理状況についてリスク管理統括責任者に報告を行うものとする。
